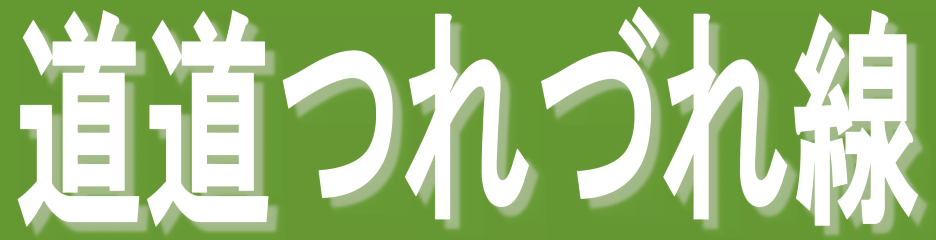北海道道路粁程表
- 2009/07/20
- 2019/12/23
「ほっかいどうどうろきろていひょう」と読みます。2009年に古書店より入手しました。
いかなる書物か。
北海道の国道・道道・主な市町村道の距離を支庁ごとに、路線別・市町村別でまとめたものです。複数市町村を通る国道・道道は、一定区間ごとに掲載しています。
表の形は、道路地図の高速道路料金表を思い浮かべると分かりやすいかもしれません(表1)。距離の単位はキロメートルです。
※北海道の高速道路料金は、NEXCO東日本の高速道路料金検索が便利です。
- 本文画像に関する注意事項を表示
- 写真+数字(写真1、写真2…)
- PCの場合、クリックすると拡大表示します。
- タブレット端末・スマートフォンの場合、写真全体を表示します。デバイスの表示サイズにより、拡大されたり縮小されたりします。
- いずれのデバイスでも、写真の下部に簡単な説明を表示します。
- 右上部のバツ印、または画面の適当な場所をクリックすると、元に戻ります。
- クリックしても拡大されない写真は、その点を注記します。
- 写真+数字(写真1、写真2…)
| 北1条 西4丁目 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |
| 231号 交点 | 0.8 | 1.9 | |
| 北1条 東8丁目 | 1.1 | ||
| 苗穂駅 入口 |
付属している各支庁の管内図が、何よりも貴重な存在です。国道は緑、道道は赤、市町村道は黒で色分けしており、表にある地点が名称とともに黒丸で記されています。
図上に描かれているのは道路と海岸線に支庁・市町村の境界だけで、縮尺も正確とは言い難い。それでも、道路の位置関係は容易につかめます。この管内図が、過去のルートを検証する上で大変参考になります。
筆者が入手したのは、写真1の1970年版です。同年4月の国道昇格前の道道が収録されており、価値の高い一冊といえます。反対に情報の新しさを考慮すれば、タイミングの悪い時期だったでしょう。
豊富遠別線の起点を探るは、冊子の管内図からヒントを得た一編です。
粁程表の発行時期
北海道道路粁程表は過去に3度発行されており、発行元は北海道です。関連する告示を引用します。1959(昭和34)年の告示のみ、原文が縦書き。
北海道告示第三百六十七号
北海道道路キロ程表を別冊のように定める。
その関係図書は、北海道土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和三十四年三月十六日
北海道知事 田中敏文
(別 冊 は 省 略)
北海道告示第365号
昭和34年北海道告示第367号を別冊のとおり改定する。
「別冊」は、省略し、北海道土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和45年2月17日
北海道知事 町村金五
北海道告示第3438号
昭和45年北海道告示第365号(北海道道路粁程表の改定)を別冊のとおり改定する。
「別冊」は、北海道土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月19日
北海道知事 堂垣内尚弘
これ以前には「北海道里程表」が発行されていました。粁程表と同様の内容と考えられ(おそらく、距離の単位が違うのではないか)、付属の図には鉄道・軌道、水路も描かれていたようです。
少なくとも、1903年(明治36年)・1910年(明治43年)・1928年(昭和3年)・1943年(昭和18年)に別冊が発行されています。北海道庁の訓令で定められました。
廃止の訓令を引用します(原文は縦書き)。
北海道訓令第十一号
庁中一般
部局
市役所
町村役場
昭和十七年北海道訓令第九十四号(北海道里程表)は、廃止する。
昭和三十四年三月二十五日
北海道知事 田中敏文
粁程表は4,000円程度、里程表は1万円台から古書店で入手できます。一部は、北海道立図書館や北海道立文書館で閲覧可能です。
利用目的
では、里程表・粁程表は何の目的に使われているのでしょう。
地方公務員の出張等に際し、陸路での旅費を計算する根拠となります。その点は、市町村が条例・規則で定めています。ただし粁程表での計算が困難な場合は、別の方法で計算することを認めているようです。検索結果を見ると、現在も根拠とする自治体が見られます。さらには、北海道里程表を根拠にする自治体も見受けられます。検索結果にてご確認ください。