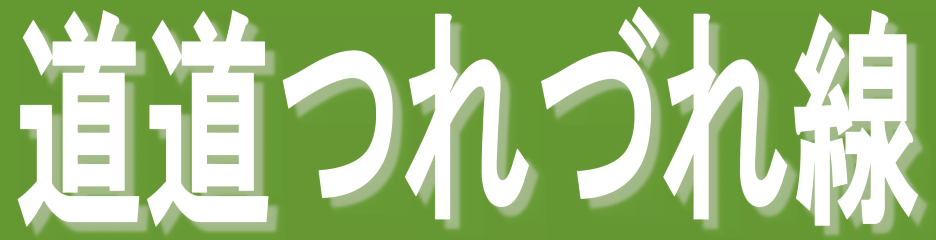『タオ―老子』と良寛
- 2009/07/31
- 2019/12/28
加島祥造著『タオ―老子』に、私は救われた。同書に出会うまでの過程を、まず書いておきたい。
21世紀が明けて間もないころ、私は苦悩の底にいた。
どう生きていったらいいか見えず、物事が何も手につかなかった。とくかく、本を読みたい…とは思っていた。
ところが、どの本を読んだらいいか皆目わからない。
札幌駅地下街アピアの書店をぶらぶらしていると、ある本の帯に書いてある言葉が私をくぎ付けにした。
文明が進歩すれば人間は幸せになる、というのは間違いだった。
帯の文が別の言葉だったら、手に取らなかっただろう。私の魂に吸い込まれてきた。その本、中野孝次著『風の良寛』を購入し、読み進めた。
同書は、良寛が遺した短歌や漢詩などから彼の生きようを述べている。何事にもとらわれず、求めず、自然と心の声に五感を傾けながら、今に生きた姿がありありと浮かぶ。良寛は「無の人」であった。著者はまた、現代人は良寛と対極にある点を指摘している。
同書の最終章で『タオ―老子』を紹介しており、老子の思想は良寛に通じるという趣旨が書いてあった。『風の良寛』読了後、私はさっそく買い求めた。
『タオ―老子』は、老子道徳経全81章を現代口語詩に訳した一冊である。漢詩を参考にしながらも、漢詩を英訳した洋書から訳しているのが特徴だ。
老子の「道(タオ)」とは無であり、「徳(テー)」とは愛だという。その深い思想は、同書を読んで感じてほしい。老子道徳経を貫く考え方は、自然の大きな働きに身を任せること、余計な欲を持たないこと、自らと他者を比べないこと、世の中は悪い面と良い面――いわば陰と陽が調和していること。あくまで私なりの解釈である。
私は以前から老荘思想に興味を抱いていた。しかし老子の現代語訳を読んでみるも難解すぎて、中途挫折せざるを得なかった。対して『タオ―老子』は、一言一句がすんなりと頭の中に沁みわたる。繰り返し読み、時間の経過とともに、身体の隅々まで行きわたるような感覚になる。そうして老子の「道(タオ)」が、いくらか自分の一部になったような気がしてくる。『タオ―老子』の思想を取り入れてから、どれだけ精神が軽くなったことか。
この二冊をきっかけに、私の読書は芋づる式に拡がり始めた。特に、加島祥造の老子をめぐる思索を書いた一連の著作は、欠かさずに読んだ。英文学者の加島祥造(1923-2015)は、老子の英訳文を読んでその思想に惹かれた経緯を持つ。
英文学者の加島祥造(1923-2015)は、老子の英訳文を読んでその思想に惹かれた経緯を持ち、晩年は長野県駒ケ根市に独居して著作を続けた。