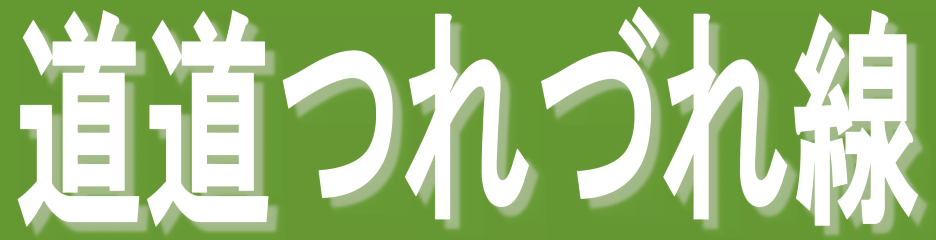5000番台の道道が存在する謎
- 2013/08/13
- 2020/07/26
4桁道道があるのはいいが、5000番台って何?
— ふくた (@Fuku_kgt) July 10, 2013
- 本文画像に関する注意事項を表示
- 写真+数字(写真1、写真2…)
- PCの場合、クリックすると拡大表示します。
- タブレット端末・スマートフォンの場合、写真全体を表示します。デバイスの表示サイズにより、拡大されたり縮小されたりします。
- いずれのデバイスでも、写真の下部に簡単な説明を表示します。
- 右上部のバツ印、または画面の適当な場所をクリックすると、元に戻ります。
- クリックしても拡大されない写真は、その点を注記します。
- 写真+数字(写真1、写真2…)
北海道には、恐ろしく大きい番号の道道があると言われます。写真1は一例です。
北海道道の路線番号は、本稿公開時点で泊共和線の1178号が最大です。ところが、北海道をクルマで通ってみると、番号表示が3000番台・5000番台の標識を見かけます。一体、どうしてなのでしょう。
道道には2種類の番号があります。
- 整理番号。道路地図など、一般的に用いられる。
- 路線番号。路線コードともいい、内部文書で用いられる。代表例は道路現況調書。
北海道の道路現況調書に後者が初めて登場したのは1971年3月31日現在の版からで、「図面対象番号」という名称でした。翌1972年3月31日現在の版以降、「路線番号」に統一されています(注1▼)。
当初の区分は、次の通りでした。
- 4000番台→主要道道。
- 5000番台→一般道道。
1978年4月1日現在の版から、区分を現行に改めます。
- 1000番台・2000番台→主要道道。
- 3000番台・4000番台→一般道道。
現況調書用番号の改定時期は定かでありません。道路現況調書は1年前のデータで刊行されるため、1977年度か1978年度と考えられます。
したがって5000番台の標識は、遅くとも1978年以前に立てられたとみてよい。主要道道の1000番台と2000番台、一般道道の3000番台と4000番台の標識設置は、早くても1978年以降になります。
1976年度末時点で、道道は932号まで認定されていました。遠い将来に1000号を超すのは間違いなく、整理番号が1000番台の主要道道を認定すれば区別できないゆえ、改定したとみられます(注2▼)。
- 注1
- 1970年以前は、整理番号と無関係に「図面対象番号」が振られていた。路線は土木現業所(現・建設管理部)別にまとまって並んでいるが、基準等は不明。
- 注2
- 1000号に達したのは1982年3月31日。翌日の主要地方道指定を経て、同年9月に1011号-1020号が主要道道の認定を受けた。現在の114号-123号。1994年9月までは一般・主要の種類を問わず、認定順に番号を割り当てていた。1994年10月に番号の再編を行い、0番台・100番台を主要道道に、200番台以降を一般道道に振り分けた。
道道には道路番号とともに管理番号があって、主要道道だと1000の桁が1、一般道道だと1000の桁が3になる。(道道美唄富良野線:1+135=1135 道道丸松線:3+826=3826) pic.twitter.com/ppGmi4RKOu
— 天羽ミズホ@1/26砲雷55N-08 (@mzh_mrssndn) February 3, 2020
路線コードの規格
そもそも部外者には、整理番号と別に番号を設ける理由が分かりません。
他県の例を調べてみました。熊本県土木部道路保全課の『道路台帳作成事務提要』(2011年度改訂)では、道路種別を次のように分類しています(表1)。また秋田県の『路線起点終点調書』では、路線コードを次のように分類しています(表2)。
| 区分 | コード |
|---|---|
| 一般国道(指定区間) | 2 |
| 一般国道(指定区間外) | 3 |
| 主要地方道 | 4 |
| 一般県道 | 5 |
| 市町村道1級 | 6 |
| 市町村道2級 | 7 |
| 市町村道その他 | 8 |
| 区分 | コード |
|---|---|
| 一般国道(指定区間・指定区間外) | 0 |
| 主要地方道 | 1 |
| 一般県道 | 3 |
表1の4と5は北海道が当初採用した番号区分と一致し、表2の1と3は、北海道の現行区分と一致します。
もっとも偶然の一致かもしれませんし、根拠となる文書類の有無も不明です。いずれにしろ、整理番号と路線名だけで、路線の識別は賄いきれない実態があるようです。
バラエティな標識の行方
筆者が知る限り、最も大きい番号の標識は日東東雲線の起点側に残る「5849号」で、番号の上部が「一般道道」の表記になっている点も特徴です。
道道のヘキサで最も大きい数字らしい。5849。 pic.twitter.com/fYepVjcZBa
— 立花ういんぐ (@KSWeb_org) November 28, 2014
道道5849号 日東東雲(にっとうとううん)線 #道路標識 https://t.co/43H9us36um pic.twitter.com/q7RbwKhqtu
— けっとる (@caitloup) August 26, 2019
3000番台~5000番台の標識は各地に残っています。ヘキサの中に路線名があるなど、変則的な標識を含め上川総合振興局管内、特に名寄・士別周辺が圧倒的に多い。
北海道建設新聞社のツイートにあるとおり、日東東雲線は新ルートが計画されており、完成後は起点側の現ルートが町道に移管される予定で、標識が消える可能性もあります。ここに限らず古い形式の標識は、いつ更新され消えてもおかしくありません。興味のある方は、見かけた時の撮影をお勧めします。
橋梁含め道路500m新設し国道39号に接続へ 日東東雲線https://t.co/QeVw12o0rR
— 北海道建設新聞社 (@e_kensin) July 18, 2019
旭川建管は、上川町内を走る日東東雲線で道路と橋梁の新設を計画している。交差する町道旭水2号線を国道39号まで延伸するもので、石狩川への橋梁新設も含め総事業費は約7億2000万円を予定している。 pic.twitter.com/TlaR6orjiL